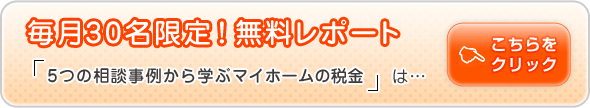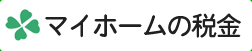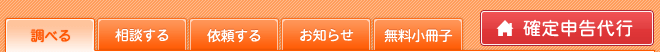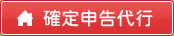住宅取得資金贈与1000万円非課税枠活用方法 平成24年版
住宅資金贈与について平成24年の税制改正により、平成23年まであった非課税制度が延長され、内容が若干変わりました。
24年改正の住宅取得資金贈与の非課税枠の制度についてはこちらをご確認下さい。
平成24年の住宅取得資金贈与の非課税特例
無料レポートでも24ページから解説していますが、住宅資金援助についてどの制度を利用すべきかを考える順序について、平成24年の改正を考慮してもう一度整理してみたいと思います。
無料レポートをまだご覧になっていない方はこちらからご請求下さい。
無料レポート
「5つの相談事例から学ぶマイホームの税金」
1.住宅援助資金について返済をする必要があるかどうか確認をします。
返済をする必要がある場合であれば、借入金とする方法を選択するしかありません。借入金とする場合には、借入金とする場合の注意事項をご確認の上、贈与と認定されないようにしましょう。
親族から贈与ではなく借入をした方
2.共有名義とする必要があるか?
資金を提供してくれた方と共有名義にする必要がある場合には、資金負担の割合に応じて共有名義にします。
共有持分とする場合
3.贈与税の非課税特例(1000万円)の適用が受けられるか?
1000万円非課税の特例はとても有利な制度なので、まずはこの制度の適用が受けられるかどうか検討します。
平成24年の贈与で省エネルギー性や耐震性に優れた住宅を取得した場合には、贈与税の非課税枠が1500万円に増えます。このコラムでは1000万円で説明をしていますが、1500万円の非課税枠の適用を受けられる方は1000万円を1500万円と読み替えて下さい。
非課税枠が1500万円となる省エネルギー性・耐震性を備えた良質な建物とは?平成24年改正
住宅取得資金贈与の非課税特例は資金援助を受けた人のその年の所得が2,000万円以下であるという条件がありますので注意して下さい。
国税庁の平成20年のデータでは所得が2,000万円を超えている給与所得者は0.5%ぐらいなようです。
以下1,000万円の非課税特例の適用を受けられることを前提とした説明になります。
5.資金援助の金額が1,000万円以下である場合には、必ず住宅資金贈与の非課税特例1,000万円の適用を受けて下さい。
住宅資金贈与の非課税1,000万円はデメリットのない制度になりますので、要件に該当するのであれば必ず適用を受けて下さい。
6.資金援助の金額が1,000万円超1110万円以下の場合には、贈与税の非課税特例1,000万円と暦年課税の適用を受けます。暦年課税とは、財産をもらった人単位で年110万円までの贈与については、贈与税を課税しませんという制度です。
1,110万円までの贈与であれば、1,000万円までは住宅資金援助非課税の特例を適用し、残りの110万について暦年課税の制度を利用すれば、贈与税の課税を受けずに住宅資金援助を受けることができます。
7.1,110万円を超える資金援助を受ける場合には、まずは、1,000万円までは住宅資金援助の非課税特例1,000万円の適用を受け、残りの金額について、将来の相続税の課税の状況などを考えながら共有名義か暦年課税か相続時精算課税制度の適用を受けることになります。
どの制度を選択した方がいいのかは、人によって異なります。相続税が将来課税されることが予想される方であれば、今後の相続税対策の選択肢を狭めてしまう相続時精算課税制度を利用しない方がいいです。住宅購入資金が足らないので贈与を受ける場合は別として住宅ローンで購入資金を確保できるのであれば、住宅ローンの返済資金を毎年コツコツと援助(贈与)するという方法もご検討下さい。
相続時精算課税制度は一度選択すると撤回をすることはできません。相続税の増税が予定されていますので財産が1億円以上ある方は相続時精算課税制度を利用しない方がいいと思います。
なお、相続時精算課税制度の住宅取得資金等に限り控除枠が1,000万円追加になるという制度は平成22年の税制改正大綱で延長されなかったため、平成21年末で廃止となりました。
そのため、相続時精算課税制度を利用した場合に、非課税で贈与できる金額は、住宅取得の場合でも2,500万円までとなります。
住宅資金贈与非課税1,000万円と併せて適用を受けると1,000万円+2,500万円で最大3,500万円まで非課税で贈与することは可能です。(1500万円の非課税枠の適用のある方は1500万円+2500万円で最大4000万円まで非課税とすることができます)
ただし、相続時精算課税制度を適用した部分については、将来相続時に元に戻して相続税の計算をしますので、その点ご注意下さい。